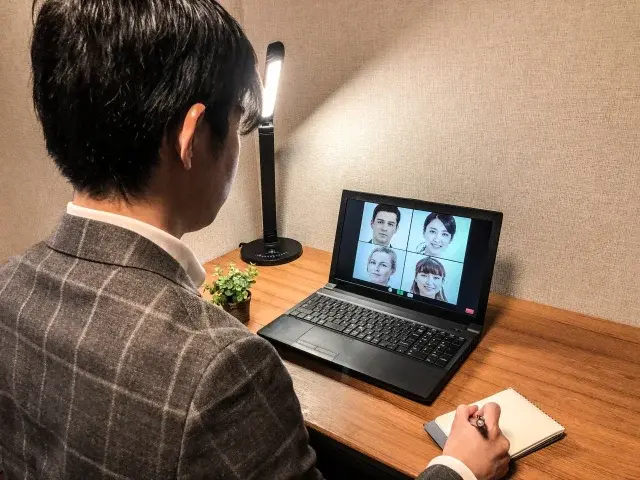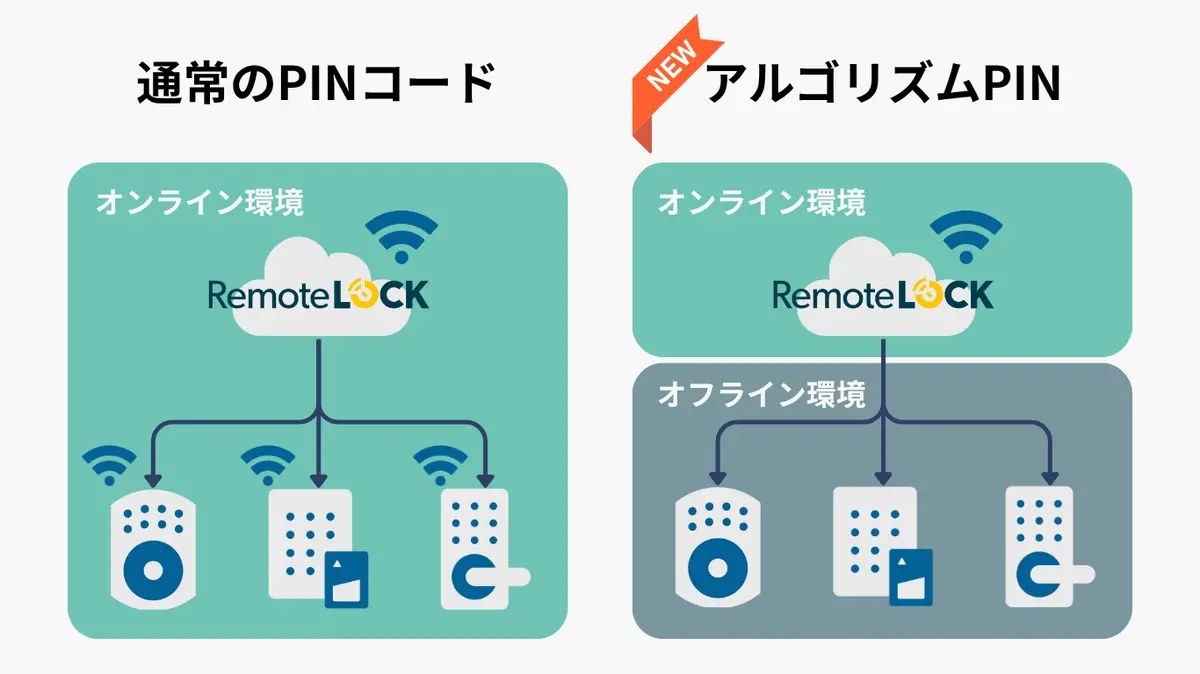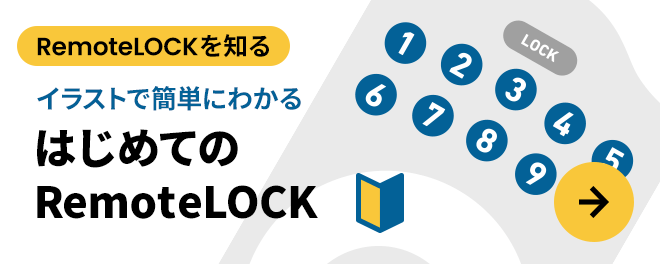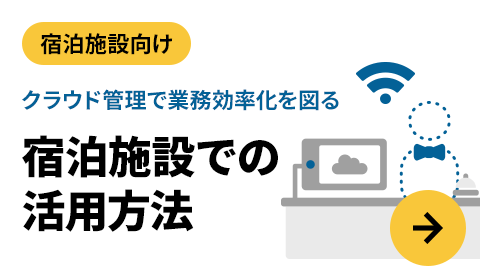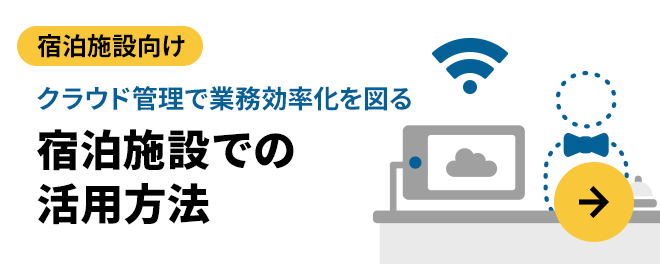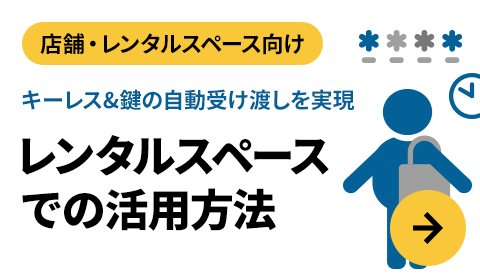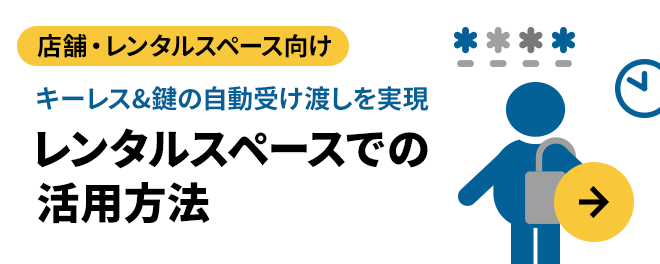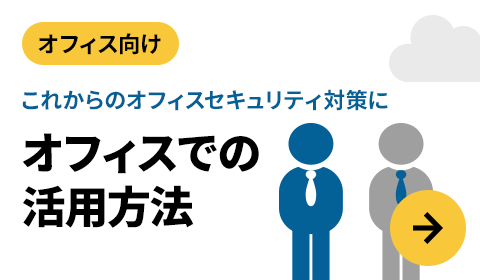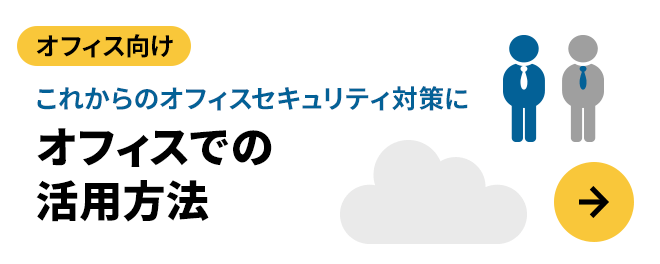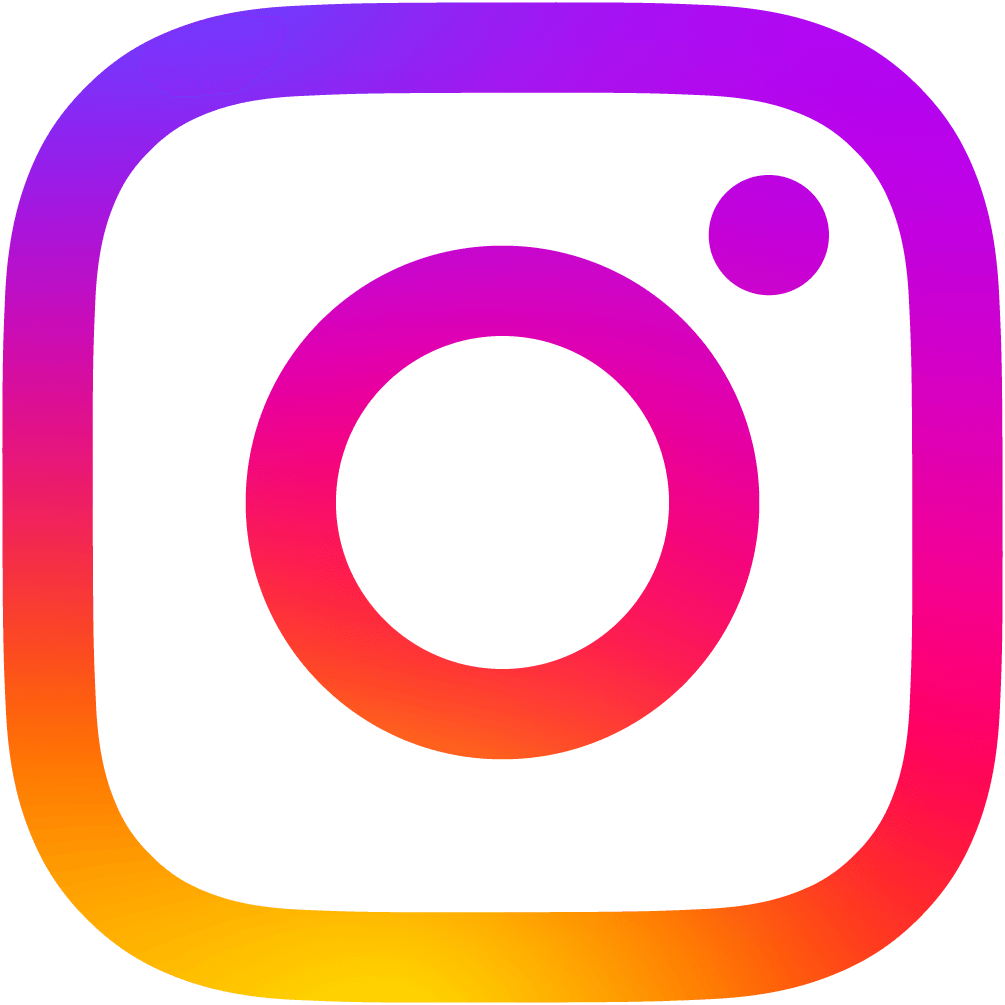【実体験】カードキー運用オフィスでのトラブル!
本トラブルに遭遇してしまったのは他でもなくRemoteLOCKチームの中の人です。鍵のトラブルについてお伝えすることも多い我々ですが、まさか実体験してしまうとは思いもよらず…。
今回はそんな本当にあったカードキー運用での鍵トラブルについてお話します。そして、こうしたトラブルのリスクとどう向き合うべきなのか、その考え方についてもご紹介します。
この記事の目次
都内で大雪の日。事件は起こりました。「カ、カードキーが使えない!」

【前提】エントランスには他社の電気錠が設置されている
我々RemoteLOCKチームがいるオフィスではフロアのドアにはもちろんRemoteLOCK(リモートロック)がついています。他方で、自社ビルではないためエントランスには他社の電気錠が導入されているため、社員はカードキーも携帯しています。
前提として、エントランスは夜8時~翌朝8時までは自動施錠されるため、この時間帯にオフィスに入るにはカードキーが必ず必要となります。
【事件当日】外は極寒。外出して戻ると…
事件が起きたその日は都内でシーズン一番の寒さとなった大雪の日でした。時刻は夜7時。大雪ということもありオフィスにはパラパラと人が残っている程度で、仕事を切り上げて早く帰った社員も多くいました。ちなみに外の様子は写真の通りです。こんな日に限って大雪でした…。
.jpeg)
筆者も早く帰ろうと思っていたのですがどうしても外せない用事があり、徒歩1分の場所にある別のオフィスまで出かけることに。もちろん遅くなってもいいようにカードキーはちゃんと携帯しました。
外に出ると一面銀世界。あまりの寒さに身震いしながら「早く用事を済ませて帰ろう」なんてことを考えていました。そして戻れたのは8時すぎ。エントランスが自動施錠されている時間です。いつものごとくカードキーを取り出し、挿入口にカードを挿し込みました。
「んっ?カードリーダーが反応しないぞ・・・」
カードを挿すとピッと音がするはずのリーダーが反応しなかったのです。エントランスは交通量の多い通りに面しているため、聞こえなかっただけかと思い、再度挿入。
「だめだ。反応しない!!!」
何度試してもリーダーは反応しません。極寒の中、絶望しました…。
【結末】無事に入れました!
残る希望は「社員がまだ中にいること」だけでした。だれかいてくれと願いを込めて恐る恐るインターフォンを押すと…。
「はい。」
奇跡的にまだ残っている社員がおり、無事、中から開けてもらえました。自宅の鍵もオフィスに置いたままだったので、家にも入れないという最悪のケースもあり得るゾッとした出来事でした。
めでたし。めでたし…とはいきませんでした。
まさかの2回目!?著者が見舞われた鍵トラブルの結末は?
結局、カードキーは磁器不良ということで交換してもらうことに。特に磁器不良の原因に心当たりはなかったのですが、今回の件で今まで以上に大切に扱うようになりました。
それから2カ月、悪夢は再びおきました。
【事件当日】セミナーから戻ると…
その日は毎月好評開催中の「民泊カンファレンス(株式会社チャプターエイトと共催 / 民泊オーナー向けのセミナー)」が開催された日でした。別のオフィスで行われたセミナーが終わり、夜8時過ぎに自分のオフィスへ戻る…
「んっ。。。カ、カードキーが使えない!!!」
こんな短期間で再び使えなくなるとは思っておらず衝撃を受けました。何かの間違いかと思い何度もカードを挿入するも結局エントランスが開くことはありませんでした。
【結末】結局締め出されたまま帰宅しました。
前回は中にいた社員に開けてもらえたので今回も…と淡い期待を抱きつつインターフォンをならすも反応はありませんでした。そう。完全に締め出されてしまったのです。
まだまだ寒さの残る3月某日、コートもなく寒さに耐えながら帰りました。自宅の鍵を持っていたのは何よりの救いでした。
どんな鍵でもトラブルはつきもの。大切なのは「予防」と「対策」

【後日談】鍵は2回目の交換へ。設備担当者も困惑。
結局私が使っていたカードキーは再び使えなくなってしまったということで、社内設備の担当者に報告し、新しいものに交換してもらうこととなりました。立て続けに2回目ということもあり、担当者も困惑するばかりでしたが何とか対応いただきました。繰り返しますがカードキーはいつも丁寧に使用・保管しています。
電気錠もスマートロックもシリンダー錠でも鍵のトラブルはあります。
鍵のトラブルは実に多様です。
・鍵の紛失
・鍵の複製と悪用>
・鍵やカードキーが壊れた
・鍵のとじ込み
・ピッキング被害
・キーボックスやスマートロックの使い方がわからない
・テンキー型の電子錠で番号を使いまわしたことで不正入室が起きた
などあらゆる問題が想定できます。しっかりとした入室管理システムであっても例えばカードキーの場合は、紛失が避けられなかったり、今回のケースのように磁器不良で突然使えなくなることもあります。
物理鍵がない電子錠の場合も電池切れにより使えなくなることも考えられます。
運用環境ごとに鍵トラブルのリスクを想定しましょう。
大事なのは「どんな鍵でも全てのリスクを完全には排除できないこと」を認識したうえで、運用環境に応じたリスクを想定し、それを予防・軽減することと、それが難しい場合は起きた時に大事に至らないような対策をとることです。
例:スタッフがチェックアウトに立ち会わない民泊の場合
リスク:「誤って鍵を持ち帰られてしまうリスク」
→回避策:「物理鍵を使わないテンキー型の電子錠を採用する」
→新たなリスク:「利用後に不正に暗証番号を使って入室されてしまうリスク」
→回避策:「暗証番号の有効期間を指定できる電子錠を採用する」
→その他のリスク:「電池切れで使えなくなるリスク」
→軽減策:「電池残量がわかる電子錠を採用する」
上記の例のように最も起こる頻度が高くかつ影響が大きいと考えられるリスクを想定して、その場合の回避策を考えていきます。回避策にも新たなリスクがある場合があるので、さらにそれを回避するにはどうするかを考えます。
完全に回避できない場合は落としどころとしてリスクの発生確率が低い方法や、発生しても被害が少なくて済む方法を考えましょう!
いかがでしたでしょうか?今回は本当にあった鍵のトラブルについてご紹介しました。意外と身近に潜んでいる鍵のトラブルについて、この機会にもう一度見直してみるのはいかがでしょうか?