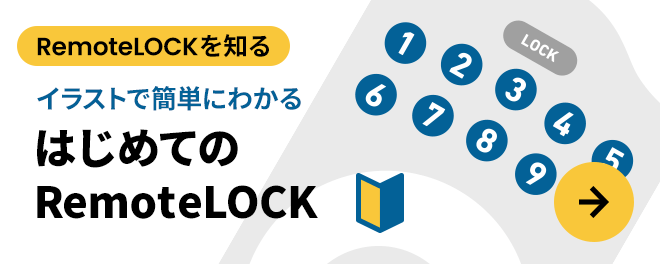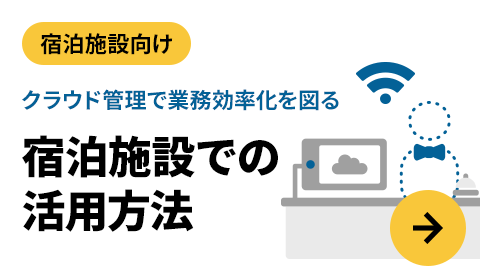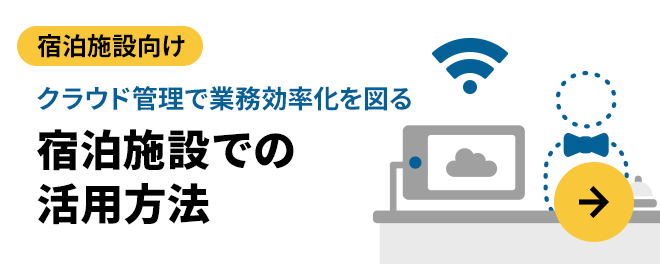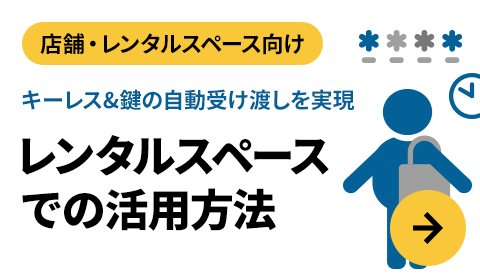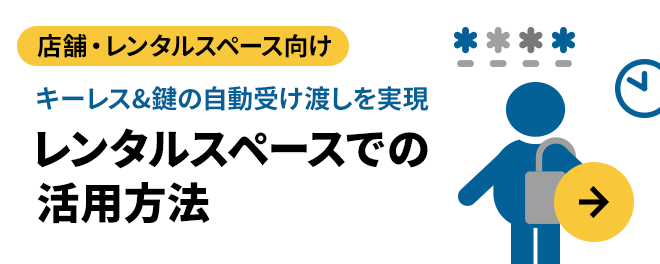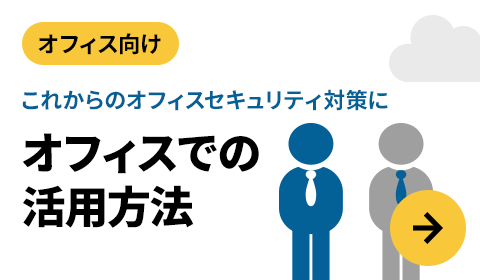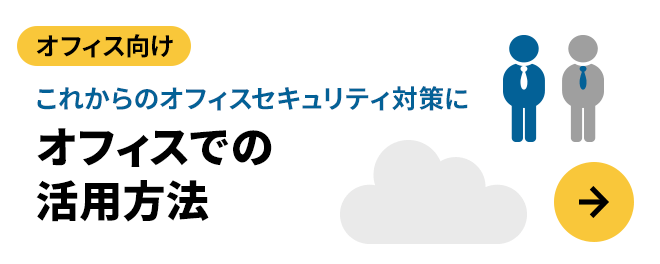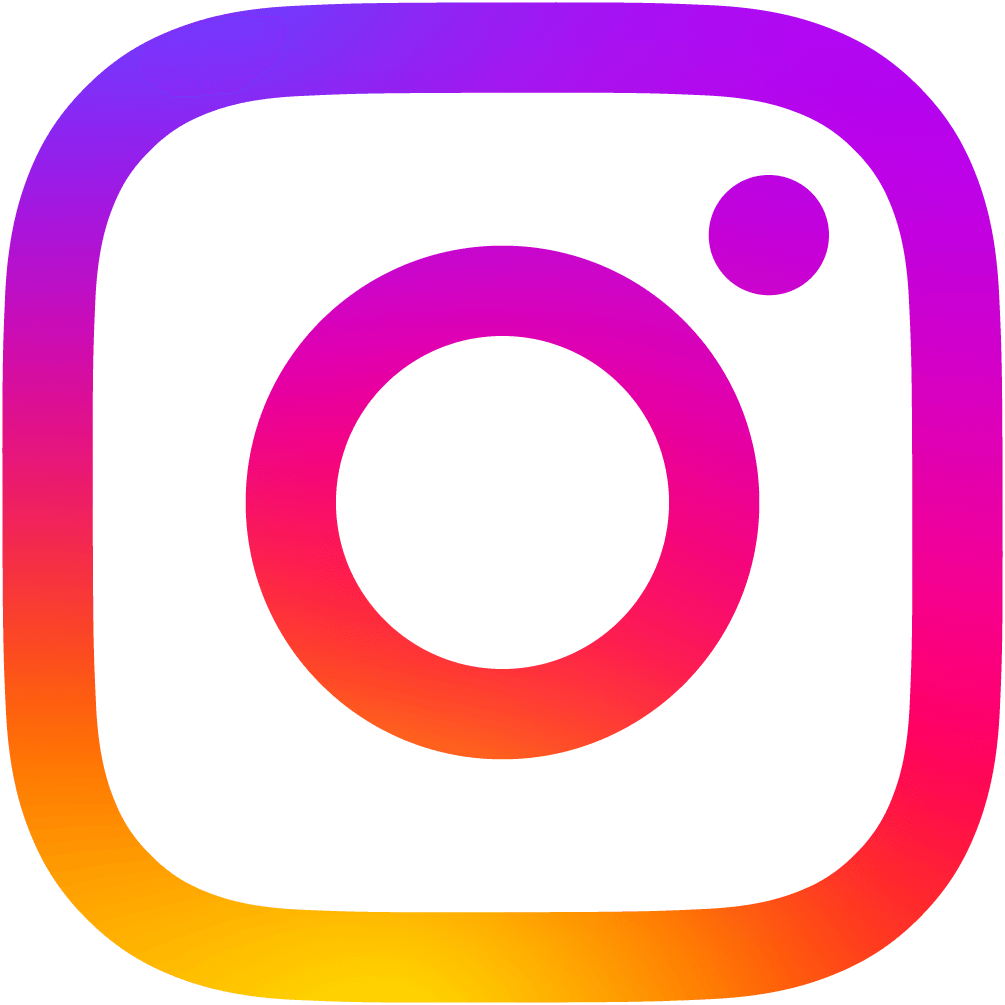公開日2024.12.25
アフターコロナ時代に求められる働く「場」のあり方とは?
2024年9月、米Amazon. com(アマゾン・ドット・コム)が世界中の従業員に原則として「週5日出社」を求める方針を示したことが、IT業界を中心に波紋を広げています。この方針には賛否両論が渦巻いており、同社では30%のスタッフが離職する恐れがあると指摘する専門家もいます。
今回は、日本におけるアフターコロナ時代のオフィス事情やこれからの働く「場」のあり方について、解説していきます。
アフターコロナ時代のオフィス事情

アフターコロナ時代における日本のオフィス事情は、働き方改革やテクノロジーの進展が相まって、大きな変化が見られています。特に新型コロナウイルス感染症の影響でテレワークが急速に普及したことから、企業や働く人々のオフィスに対する考え方に変化が生じました。
オフィスの役割の変化

コロナ前まで、オフィスは共に働く者同士が時間や場所を共有するスペースであり、原則として定時に出勤し、仕事が終われば退勤する、というのが一般的なワークスタイルでした。ところが、コロナ禍において、感染症予防の観点から、リモートワークやテレワークが急速に普及したことで、オフィス=仕事をする場、という概念が崩れたことがオフィスに対する考え方に変化が生じた理由です。
その結果、今ではオフィスの役割は単なる「仕事をする場」ではなく、社員同士が連携を深めたり、創造的なアイデアを産み出すためのコラボレーションの場としての役割が重視されるようになっています。また、重要な会議や研修、新人教育、チームビルディングの場としても積極的に利用されています。
テクノロジーの進化

テクノロジーの進化がオフィスの役割変化を可能にしています。特にコロナ禍で普及したビデオ会議ツールが多様なワークスタイルを支えています。2010年代後半からの働き方改革により、効率的な業務管理とチーム連携を実現するビジネスチャットツールやプロジェクト管理ツールが広く利用されています。
代表的なオンラインツール
- ビデオ会議ツール
Zoom、Skype、Google Meet、Microsoft Teamsなど - チャットツール
Slack、LINE WORKS、Microsoft Teams、Chatworkなど - プロジェクト管理ツール
Trello、Asana 、Backlog、Notionなど
テクノロジーの進化を活かした多様なビジネスツールが、アフターコロナとなった現在でも、リモートワークとオフィスワークのスムーズな連携を可能としています。
ハイブリッドワークの拡がり
ハイブリッドワークとは、自宅やシェアオフィスなどオフィスと離れた場所で働くリモートワーク・テレワークと、出社型のオフィスワークを組み合わせた働き方です。内閣府が行なった調査では、2023年3月におけるハイブリッドワークを実施している人の割合は、全国で25.5%、東京23区だと42.2%でした。
これは、新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行されたのが2023年の5月でしたから、その直前のタイミングでの数字となります。ハイブリッドワークを実施している人の割合は、コロナ前の2019年12月では、全国で7.5%、東京23区で14.3%でしたから。その間の約3年数カ月で、いかにハイブリッドワークが拡がったのかがわかります。
テレワークから出社シーンの増加傾向
2024年から世界的にオフィス回帰が強まっており、ある調査では日本でもハイブリッドワークが減少し、フル出社が増加しています。別の調査では、大企業の約60%、中小企業の約40%がオフィス回帰を進めているか検討中です。

オフィスのトレンドとして、固定席を持たずに好きな席で働くフリーアドレスが多くの企業で採用されています。導入企業は50%~80%で、座席設定率は平均60%です。
オフィス回帰が進めば、フリーアドレスを導入している企業によってはオフィスの座席数が不足するという事態が考えられますので、今後はオフィスのレイアウトや運用方法をいかに最適化していくかということが重要な課題となります。
運営に欠かせない鍵なら『RemoteLOCK(リモートロック)』
- ・予約者ごとに異なる暗証番号を発行可能
- ・予約期間外は入室不可に!期間外の不正入室の心配はなし
- ・予約システムとの連動で番号を自動発行
▼資料(PDF)をダウンロードする
進むオフィススペースの最適化

コロナ禍を通じてリモートワークやハイブリッドワークが一定程度定着する中、多くの企業でオフィスを縮小したり、フリーアドレスの座席数を減らしたり、といった取り組みがなされました。そんな中でのオフィス回帰の流れに対する企業の対応について解説します。
サテライトオフィスの活用
最近のオフィス回帰の流れの中で、注目されているのがサテライトオフィスの活用です。サテライトオフィスとは、本社オフィスとは別に分散して設けられた小規模な拠点で、働き方の選択肢を広げる手段として需要が高まっています。
社員が自宅や居住地から通いやすい場所に設置されることが多く、社員の通勤の負担を軽減しながら、本社オフィスのスペースを拡大する必要がないため、コスト効率の面でも優れているといえます。テレワークで不足しがちな直接的なコミュニケーションを補う場として機能しつつ、対面交流によってチームワークを促進するなどの効果も期待できます。
社員管理をどうするかという点と、いかにセキュリティを確保するかという点が、サテライトオフィスの課題であるといわれています。

シェアオフィスやコワーキングスペースの活用

シェアオフィスやコワーキングスペースは、企業が自社オフィスを設ける代わりに、複数の企業や個人が共有して利用する施設で、すぐに利用でき、期間や人数に柔軟に対応できる点と、コスト効率の高さから人気となっています。
新たにオフィス機器や通信設備などを整える必要もありませんし、社員の居住地に近い施設を選択すれば通勤時間を短縮することもできます。本社オフィスやサテライトオフィスと異なり、異業種や多様な働き方をする人々が集まる場ですから、新たなコミュニケーションやイノベーションの促進につながることも期待できます。本社オフィスとシェアオフィスやコワーキングスペースを組み合わせることで、拠点分散型の柔軟な働き方を支援することができます。
オフィスレイアウトの見直し

オフィス家具大手のイトーキが展示場的に利用している本社オフィスを見学する経営者の数が2年間で4倍以上に増えたといいます。オフィス回帰が進む中でオフィススペースの効率化をはかる必要が生じることは明らかですが、もう一つの視点として、いかに社員が出社したくなるオフィスにするかという視点も重要です。
また、第1章でも触れたように、オフィスの役割が単なる「仕事をする場」ではなく、社員同士が連携を深めたり、創造的なアイデアを産み出すためのコラボレーションの「場」としての役割が重視されるようになっています。会議室の数を減らすなどしてスペースの効率化を進める一方で、新たにコミュニケーションスペースやカフェスペースなどを新設し、社員同士の交流を深めることができ、社員が出社したくなるような環境を整える企業が増えています。
テレワーク移住の促進と地方分散

テレワークの普及が進む中で、テレワーク移住や地方分散も注目されています。都市部の生活コストや通勤負担を軽減し、地方での豊かな暮らしを実現する新しいライフスタイルとして注目され、全国各地に拡がっています。特に、自然豊かな地域やリモートワーク環境が整備された地方都市が人気となっています。地方自治体も移住促進策を展開しており、補助金制度の充実、サテライトオフィスの設置、移住者向けの住居提供などを通じて働く環境を整えています。
また、オフィスの地方分散を進める企業も現れてきています。都市部の本社機能を縮小し、地方にサテライトオフィスを設置することで、社員の生活の質を向上させると同時に、地方活性化にも貢献することができます。さらに、企業のコスト削減やリスク分散にもつながるというわけです。
これからの働く「場」に求められること

第3章では、オフィスという空間だけにとどまらない、これからの働く「場」というもののあり方について、補足的な視点から解説します。
いかに社員のモチベーションを高めるか?

コロナ禍で多くの企業は新卒社員のテレワークを基本とし、コミュニケーション不足や不安が生じました。企業も新人研修が難しく、一体感が薄れる問題がありました。アフターコロナでオフィス回帰が進む中、働き方は多様化し、社員のモチベーション向上やコミュニケーション活性化がどの業界でも課題とされています。
オフィスの見直しにとどまらず、ある企業では「ファミリーデー」や「社内イベント」でコミュニケーションを活性化しています。広告会社の社長によると、週1回の自由参加の社員交流会も始めたそうです。
モチベーションを高めるための取り組み例
- 福利厚生の充実
- 社内コミュニケーションの活性化
- スキルアップのための研修・教育制度
- 成果に応じたインセンティブ制度
- 明確な目標設定とフィードバック
AIやIoTを活用したスマートオフィス化の流れ
働き方やオフィス利用のあり方が多様化する中で、AIやIoTを活用したスマートオフィス化も進んでいます。スマートオフィスは、テクノロジーを駆使して効率的で快適かつ安全な職場環境を実現する取り組みで、特に業務効率化や生産性向上、従業員の安全管理・健康管理の観点から注目されています。
AIを活用したスマートオフィス化

例えば、AIを活用した空席管理システムは、リアルタイムで席の空き状況を把握し、フリーアドレスのオフィスの効率を高めています。また、会議室予約やスケジュール調整をAIが自動化し、無駄な時間を削減するシステムも登場しています。さらに、データ分析を活用して業務プロセスの課題を特定し、AIがより効率的な業務運営を提案するケースもあります。
スマートロック(RemoteLOCK)を活用したスマートオフィス化

社員の安全と健康という面では、IoT機器であるスマートロックによる入退室管理を挙げることができます。スマートロックを導入し、会議室予約システムと連携することで、会議室や共有スペースをより効率的に安全に管理することが可能です。
またオフィスの効率化が進む中、最近では受付を無人化したり、非対面化したりする企業も増えています。スマートロックを自動受付システムと連携することで、受付が無人でもオフィスの入口を安全に管理することが可能となります。さらに、第2章で触れたサテライトオフィスではセキュリティの確保が大きな課題でとなっています。スマートロックがひとつの最適解となるでしょう。
このようなAIやIoTを活用したスマートオフィス化は、企業にとって、生産性向上とコスト削減を両立する新しいオフィス運営の形として、今後さらに広がっていくでしょう。
【まとめ】キーワードは”多様性”
今回はアフターコロナ時代のオフィス事情と、これからの働く「場」というもののあり方について、いくつかの切り口から解説してまいりました。テレワーク、ハイブリッドワーク、フリーアドレスなど、コロナ前まではそれほど普及していなかった働き方やオフィスのあり方が急速に拡がったことで、企業にも働き手にもさまざまな新しい選択肢が生まれました。この変化が、これからの、多様性に富んだ、より良い企業文化の醸成につながっていくことを願います。